𦱳衝撃の異国文化
明治7年、名古屋の旅館・森田屋の長男として生まれた森田吾朗(本名:川口仁三郎)は、音楽の才能に恵まれ、手先が器用で物づくりが得意な少年でした。
14歳の頃、彼は二絃琴や明笛を演奏するようになっていました。
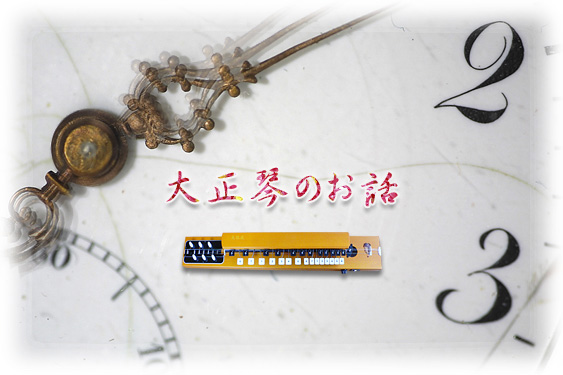
そして25歳の時、吾朗は演奏旅行のためにヨーロッパに渡ります。
そこで吾郎が見たものは、音楽が日常生活に溶け込み大衆に浸透して生活に潤いを与えているという事実でした。
吾郎は、異国の音楽文化のレベルの高さに衝撃を受けます。
「日本では、学校で唱歌を学ぶためにオルガンやピアノなどの洋楽器を用いているのに、家庭で復習しようと思っても箏・三味線しかない。学校と家庭の音楽環境が違うのでは音楽界の発展はない。高価なピアノなどに代わる、安価で、洋楽の復習ができる楽器を作らなければいけない」
吾郎はそう決心しました。
𧘕タイプライターに閃く

吾郎は演奏旅行中に、ヨーロッパでは文章作成のために日常使われているタイプライターを見て、新しい楽器のメカニズムのヒントを得ます。
帰国後、吾郎は新しい楽器作りに取りかかりました。
そして、当時日本で人気が高く自らも演奏した二絃琴を基本にして、タイプライターからヒントを得たボタン装置を組み合わせて、鍵盤付き弦楽器を完成させました。
大正1年9月9日に全国で一斉発売され、その日が重陽の節句(菊に長寿を祈る日)であったことから菊琴と名付けられたこの新しい楽器が、後に
大正琴の名で親しまれ百万人を越える愛好家を誕生させることになります。
蠃現代琴事情
現代の大正琴は、木製の空胴に5〜6本の金属弦を張り27個の鍵盤(キー)を備えた、軽量でコンパクトな楽器となっています。
友弦流ロゴ入り大正琴「桜華」
(本体サイズ 72cm)
演奏方法は、左手で鍵盤を押さえ、右手に持ったピックで弦を弾きます。向こう弾き(手前から向こう側へピックを動かす弾き方)が基本となります。
大正琴は邦楽と洋楽が混在する時代を経て、和・洋いずれの楽曲にも適するように改良されてきました。
そのため、演歌・童謡・民謡からクラシック・ラテン・ポップス・最近のヒット曲まで、幅広いジャンルの楽曲をカバーできる点が特徴です。
大正琴の音域は2オクターブで、昭和50年代には従来のソプラノ音域の大正琴に加えて、アルト、テナー、ベース音域の大正琴が開発され、アンサンブル(複数の人が同時に演奏)も可能となり、一人で弾く楽器からグループで合奏可能な楽器に変貌を遂げました。
觳大正琴の特長(その1)
演奏会では、数十人で一斉に合奏するスタイルが主流になっています。うまく演奏するためには、呼吸を合わせることが大事です。そして、チームワークの輪が広がります。だから…
大正琴をする人は、共通の目的を持ってつながる仲間が自然にできます。
觳大正琴の特長(その2)
多くの楽器は、始めたばかりの時はまともに音が出せなくて苦労しますが、大正琴は最初から簡単に音が出せ、すぐに、ある程度弾けるようになります。だから…
三日坊主にならず、成果が目に見えて表れますので“やりがい”が生まれます。
觳大正琴の特長(その3)
楽譜が理解できない人でも、ドレミの音階に対して数字の1,2,3…が分かりやすく鍵盤に表示されていて、何歳でスタートしても上達できる珍しい楽器と言えるでしょう。だから…
大正琴をする人は、子供からお年寄りまで、老若男女を問わず人生を楽しんでいます。
觽おまけに…
大正琴を演奏する時は、楽譜を見て、鍵盤を押して、弦を弾くという両目、両手の動作を素早く繰り返しますので、脳がほどよく刺激されて、頭の体操(脳トレーニング)が自然にできてしまいます。
大正琴とは、こんな素晴らしい楽器です。あなたも大正琴を始めてみませんか?
このモバイルサイトやPCサイト(
URLはこちら)で大正琴の世界をじっくりと覗いてみてください。
迷っておられる方やご質問がある方は遠慮なく
螾お問い合わせください。





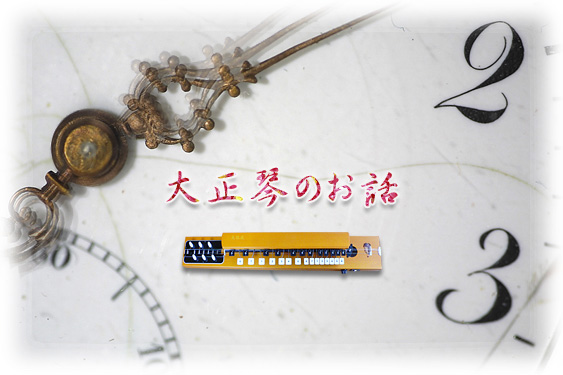 そして25歳の時、吾朗は演奏旅行のためにヨーロッパに渡ります。
そして25歳の時、吾朗は演奏旅行のためにヨーロッパに渡ります。 吾郎は演奏旅行中に、ヨーロッパでは文章作成のために日常使われているタイプライターを見て、新しい楽器のメカニズムのヒントを得ます。
吾郎は演奏旅行中に、ヨーロッパでは文章作成のために日常使われているタイプライターを見て、新しい楽器のメカニズムのヒントを得ます。


